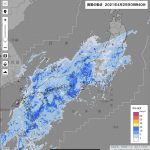先日行ったしょうけい館(傷痍軍人史料館)では、日本で最も有名な傷痍軍人として水木しげるの名前を挙げた。
事実、郷里の鳥取県境港市には水木しげるの顕彰碑があり、町おこしにはゲゲゲの鬼太郎が使われている。ついでにアニメでは猫娘も昔の面影ない程萌え化されてしまった。(それが良い悪いの話は触れない)
今回も「有名人系傷痍軍人」の話を・・・
その前にこの時期の時代相についておさらいしておくと、昭和12年の盧溝橋事件日中戦争が始まって以降、昭和13年も後半になるとどんどん戦時色が濃くなっていく。
8月16日にはヒトラー・ユーゲントが来日、北原白秋が歓迎する曲を書いている。
この時期の北原白秋は最晩年にあたり、糖尿病の合併症でほとんど目が見えなくなっていたが、精力的に詩作に励んでいたのだという。また、国家主義に傾倒していた時期でもあった。
また、9月には従軍作家が国策を担って戦地に旅立っていった。
 さて、昭和13年10月4日の東京朝日新聞の7面は、連載小説あり、小説家のエッセイあり、下半分は大々的に「講談倶楽部」の広告となっている。
さて、昭和13年10月4日の東京朝日新聞の7面は、連載小説あり、小説家のエッセイあり、下半分は大々的に「講談倶楽部」の広告となっている。
この面の執筆陣は川端康成(当時39歳)が文芸評論として芥川賞候補作となった上田広「黄塵」を評している。
この上田広は鉄道教習所機械科を卒業して鉄道省に勤めており、やはり「従軍作家」として国策を担い戦地で活躍していた。
また、宮城道雄(当時44歳)が、奈良へ行った時の事を書いている。春日大社では鹿に煎餅をやったり、大仏の頭を撫でてみたかったができなかった旨のことを書いている。
さて、本題となるのは左側に4段抜きで比較的大きく扱われている「タクトを左手に」という随筆である。
 指揮者なら指揮棒は右手に持つもの。
指揮者なら指揮棒は右手に持つもの。
それが出来ないのは、この記事の筆者である伊藤武雄が第2次上海事変で従軍し、右手を失ったためである。
第2次上海事変については拙ブログでは本年11月27日の項でも触れているが、この時の「上海南駅の赤ん坊」のフォトスクープが「LIFE」誌に掲載され、アメリカにおける決定的な対日感情の悪化につながっている。
応召前までオペラ歌手として活躍していた伊藤は、傷痍軍人として除隊後は母校である東京音楽学校(現在の東京藝術大学音楽学部)に戻り、助教授として後進の育成にあたっていた。
ちなみに、音校の奏楽堂は現在でも上野の森に残っており、重要文化財として保存され現在でもコンサートに使われている。
 11月24日に博動の駅の公開があった時には整理券が無くて入れなかったが、その向かいにある音校の奏楽堂は決死していた。
11月24日に博動の駅の公開があった時には整理券が無くて入れなかったが、その向かいにある音校の奏楽堂は決死していた。
(決死モデル:チームPみく)
記事の冒頭にある「白衣の勇士を迎えるので合掌指揮を頼まれ・・・」とは、明治23年(1890年)に建てられ築50年になろうとしていたこの奏楽堂で行われたものであろうか。
また、題字横にはたどたどしい字で肉筆署名しているが、利き手変換もまだ途上であった時期だったのであろう。
傷痍軍人となってしまった海外の音楽家の例は伝え聞いていたようで「欧州戦争(第1次世界大戦)後。片手の指揮者がいたのは聞いたことがある。ウイーンには左手だけのピアニストもいるというそうだ」と書いている。
ただ、戦傷のショックはまだ伊藤の頭の中には去来していたようであるが、「そこをもう一歩進んで、大きく行きたいものである」と、努めて前向きに生きようとしていたことがわかる。
彼の中に教訓として残っていたのが、応召前に見た片足のキリギリスで、足と翅で鳴くものだと思っており、鳴かない(鳴けない)だろうと思っていたら見事な声で鳴いていた。その一匹の昆虫は今でも私の心の中に住んでいる、と記事は結んでいる。
 戦後すぐに「子供のための音楽教室」発足に加わるなど声楽界発展のために尽力した。
戦後すぐに「子供のための音楽教室」発足に加わるなど声楽界発展のために尽力した。
Wikipediaにも載せられているこの写真は、昭和26年当時に全国で有名だった「伊藤武雄」氏が一堂に集ったものであり、左から金沢大教授、大阪商船社長、中国研究者、声楽家、名古屋大学教授の、それぞれ「伊藤武雄」氏であった。
昭和51年には勲四等旭日小綬章にも叙せられている。
そして昭和62年、「義肢装具士」制度発足の年に永眠。享年82歳。