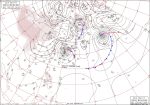「義手と義足の昭和史」今回は昭和30年代に入りたい。
とは言っても昭和30年2月20日の記事なので、日本の年度で言えばまだ昭和29年度が続いているというあたりである。
 曰く、「見た目だけではなく、触った感じまで本物そっくり」の義手ができたのだという。純粋なプラスチックでできたのはこれが世界で初めてだったのだそうな。
曰く、「見た目だけではなく、触った感じまで本物そっくり」の義手ができたのだという。純粋なプラスチックでできたのはこれが世界で初めてだったのだそうな。
「毛穴も付けられる」というから大したものである。
義手だけではなく、
「生まれて二十七年間、片耳が無いので中耳炎と偽って包帯を取ったことが無かったのだが、生まれて初めて科学を信じる事ができた」
という方もおられ、現在で言うエピテーゼの世界の話になるのかもしれない。
開発者である秋山太一郎氏は、Wikipediaにも項目が立っており、
医療用高分子の研究の分野で活躍し、血液樹脂、合成高分子、医用シリコーン、医療用の生体モデルなどを開発し、医療技術の向上に貢献した。
という功績を残され、後年は郷里の山形県鶴岡市で、地元新聞の社長を務められたのだという。
さて、義手や義足を「魅せる」時代にまで進化した2017年の現在、欠損バーで琴音ちゃんやぽわんちゃんの義手を毎度毎度「握手会」と称してお触りしているが、毛穴があったという記憶はない。
テレビ塔みてまーす
小さ…………
何でもないです(琴音) pic.twitter.com/2ypoi8P64X— 欠損BAR ブッシュドノエル公式 (@bucheden0el) 2017年5月21日
きっと、毛穴まで作ったはいいが、実用上何か問題が発生したということなのかも知れない・・・
さて、他の記事に目を移すと、「興安丸、一路故国へ」というニュースが目に付く。
終戦から10年が経ち、経済白書には「もはや戦後ではない」と書かれたこの年、まだ満州など外地からの引き上げは続いていたのである。
Wikipediaの「興安丸」の項目を見ると、昭和32年まで引き揚げ船として使用していたようである。
また、「岸壁の母」のモデルとなった女性は、昭和56年になってもなお息子の帰還を待っていたという。
この頃の中国と言えば、中ソ蜜月時代で日本との国交はなく、毛沢東による「大躍進政策」で大量の餓死者を出していた時期である。
そんな「竹のカーテン」の向こうで、日本人は果たして生きながらえる事ができていたのか。
そのあたりが、立命館大学の研究者によって「戦後中国における日本人の引揚と遣送」(立命館文化言語研究第25巻1号)として触れられている。
他の記事では「活気あふれるソ連・中国音楽界」とあるように、東西冷戦のさなかにもまだ「進歩的文化人」が社会主義を称揚し「言論の自由」を謳歌する雰囲気はあったようである。
このような雰囲気の中から、数年後「朝鮮人の帰還事業」が始まることになる。。。