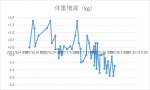平野啓一郎「かたちだけの愛」でいう「南千住のセンター」、GIMICOさんが言う「南千住のテーマパーク」であるところの、現在の義肢装具サポートセンターの経営母体である鉄道弘済会は、昭和7年に誕生している。
またJRどころか日本国有鉄道もなく、「鉄道省」というお役所だった時代のこと。
その開闢にかかる事情を「鉄道弘済会三十年史」から拾い読みしてみると、以下のようなくだりがある。
こうした一群の中で、片岡謌郎はつねに、「役人になったからには出世することなどは念頭におかず、社会のためになる仕事をやろうではないか」と唱導した。当時、若いこれらの一群は非常に片岡の言に共鳴し、また感化されるところが多かった。その片岡謌郎が、大正十一年に東鉄上野運輸事務所の営業主任になった。まだ年は二八才であった。この青年の眼に映じたものはなんであったかというと、鉄道業務に従事中に、彼の部下、同僚が鉄道事故で手や足を失って不幸な公傷退職者となり、路頭に迷っている姿であった。これを救済しようと考えてもよい案がなかったが、たまたま片手片足なくとも鉄道の売店で物を売ることならばできるではないかということを思いついたのだった。
文中の「片岡謌郎」氏について、「戦前期日本官僚制度の制度・組織・人事」(秦郁彦)から拾い読みしてみると、旧制二高から東京帝大法学部を経て、大正8年10月に高等文官試験に合格し鉄道省入りしている。
そして沼津駅助役を皮切りに、昭和16年に勅任監察官で鉄道省を退官しているようである。
そして鉄道弘済会三十年史が刊行される昭和37年には、「運輸調査局理事長」の肩書となっている。
「出世することなどは念頭におかず」なんて言う割には結局、運輸調査局に天下りはしてるのね・・・ というのはさておき、かように鉄道の職場とは、手足の切断事故が後を絶たない職場であったということがうかがえる。
 今回紹介する記事に出てくる方もまた、鉄道作業中に足を失われた方である。
今回紹介する記事に出てくる方もまた、鉄道作業中に足を失われた方である。
昭和29年3月6日の朝日新聞の東京版に、荒川区の三河島の男性(47)が終戦の前年つまり30代の後半に、巣鴨駅で日通職員だった時に貨車の事故で足を切断し、それ以来義足で暮らすことになったということが報じられている。
以降、工員として家族を養ってきたのであるが、なにぶん零細工場の密集する低所得地帯であり、玄関には靴を入れるスペースもない。
それで、靴と一緒に義足も外の靴箱に入れたら盗まれたのだという。
盗まれた本人も言っているが、本当に、義足なんか盗んで何の役に立てるつもりだったのだろうかというのが、まず第一に出てくる感想である。
この日の他の記事に目を移すと、港区立朝日中学校で、栄養状態の悪い生徒のための料理教室を学校で行うという記事が出ている。
この学校のある白金三光町と言えば、現在の美智子皇后陛下も当時は大学生として通っていたであろう聖心女子学院のある場所でもあり、貧民窟もあったということは今の感覚では理解しがたくはある。
 さて、この3月6日の記事は、都内でそれなりの反響を呼んだようで、3月9日の東京版には、被害に遭われたこの工員の方に、続々と浄財が寄せられたり、義足の制作を申し出る人もあったようであり、当人も「自分の不注意から起こったことであるにもかかわらず、何と御礼を申し上げていいか分からない」というコメントが寄せられている。
さて、この3月6日の記事は、都内でそれなりの反響を呼んだようで、3月9日の東京版には、被害に遭われたこの工員の方に、続々と浄財が寄せられたり、義足の制作を申し出る人もあったようであり、当人も「自分の不注意から起こったことであるにもかかわらず、何と御礼を申し上げていいか分からない」というコメントが寄せられている。
他の記事に目を移すと、この日の東京版のトップには錦糸町の白木屋デパートの写真がある。
戦後10年が経とうとしても、空襲で焼けた姿のままとなっていることが報じられている。
この事は、Wikipediaの「白木屋(デパート)」の項目にもあり、曰く、
JR錦糸町駅前の城東電気軌道錦糸堀停留所に開設した店舗を借りて出店していたため[39]、店舗の1階に電車が発着していた。戦後も戦災で焼けた状態のまま補修工事がほとんど行われぬまま1階のみが使用される状況が続いたが、改修されて墨田区内で当時唯一の大型店であった江東デパートとなった[37]。解体後、現・東京トラフィック錦糸町ビル(東京都交通局のビル)。
ということが書いている。
 果たして、それから2週間とおかず3月17日の東京版の記事では、早速新しい義足ができた旨が報じられている。
果たして、それから2週間とおかず3月17日の東京版の記事では、早速新しい義足ができた旨が報じられている。
当人も大喜びで、「私の生活ではこんな高価な義足は作ることができなかった」と言っている。
めでたしめでたしで一件落着となった。
隣の記事に目を移すと、「青ヶ島から本社にSOS」として、11月から船が決行して食料や生活必需品が全くなくなっていることが報じられている。
え? 11月から・・・?
今でこそ、就航率こそ低いものの「あおがしま丸」が1日1便八丈島から出ており、空の便も「東京愛らんどシャトル」というヘリが出ているが、そんな現代からすると考えられないような話である。
この状況は、翌昭和30年に「青ヶ島の子供たち 女教師の記録」として映画化されている。
Wikipediaで見る限りでは、
ところが、その年の冬は例年にまして島の海が荒れて貨物の定期便さえ辿り着けなくなり、島の人々は飢えに苦しむ。節子からの手紙が来なくなったことで島の窮状を知った日吉台小学校の子供たちはホームルームで島に支援物資を送ろうと決める。それを提案したのは、クラスに溶け込めなかったのを節子やクラスメートに励まされて立ち直った島田少年だった。彼の父は航空貨物を扱う会社の社長であり、航空便で島に救援物資を投下しようということになる。
完全に外部との連絡が途絶した青ヶ島村では、島の窮状を前にして何も出来ない節子が絶望していた。節子は安成に教師を辞めたいと弱音を吐き、安成に諭される。その節子の耳に、救援物資を満載した飛行機のプロペラ音が轟く。島のあちこちに投下される救援物資が、日吉台小学校の子供たちからの贈り物であることを知った節子は、希望を取り戻すのだった。
いやはや何とも・・・ としか言いようのない状況である。





-150x96.png)