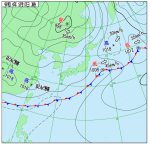3回目となる今回は、戦後となる昭和20年代から1つおおくりしたい。
昭和23年6月6日の読売新聞で、写真付きで大きく扱われている。
 「義手に血は通う」と題したこの記事は、レントゲンでの火傷が原因で手を切断したレントゲン技師と、熱意のある義肢メーカーの社員が出会い、練習を重ねることにより、フック義手でもかなりの事ができるようになった・・・ という記事である。
「義手に血は通う」と題したこの記事は、レントゲンでの火傷が原因で手を切断したレントゲン技師と、熱意のある義肢メーカーの社員が出会い、練習を重ねることにより、フック義手でもかなりの事ができるようになった・・・ という記事である。
一般的に、レントゲン技師というのは、手の切断のリスクもあるような過酷な仕事なのだろうか・・・?
そのあたりを調べてみると、放射線によるやけどというリスクがあったようである(レントゲンとX線のリスク意識(第2回)改訂版 – サイエンスの森より)。
ともあれ、終戦から3年、傷痍軍人も正に労働力としての年齢であり、この記事で勇気づけられた義肢ユーザーはそれなりの数に上ると想像される。
ところで、「義肢メーカーの社員」が義肢装具士だったといえば、当時は「義肢装具士」という制度はなかったようである。
「AUGKING-LAB」というページによれば、義肢装具士法は昭和62年(1987年)というかなり後に制定されたとのこと。
この記事の話に戻ると、義肢メーカーの社員によると「アメリカにも引けを取らない義手ができたと思う。自分でビフテキを切ることだってできる。ただ、義手を作ることもできない貧しい人がまだたくさんいる」とのこと。
このレントゲン技師は、読売診療所に勤めていたが受傷を機に本社の資料室に勤める事ができたという、比較的恵まれた、それこそ「ビフテキ」を食べ、パイプ煙草を吸うことのできる生活環境にあったのは確かであろう。
他の記事に目を移すと、「ヤミ物資」に関する記事が2つ出ている。
1つは、東京中央卸売市場で魚の横流しをしていた職員にガサ入れしたというもの。
もう1つは、裁判所判事によるヤミ物資に関する弾劾裁判で、Wikipediaの弾劾裁判所の項にも書いている事件である。
1948年11月27日、闇物資の魚粕やスルメなどの買い付けのため無断欠勤して前任地の秋田市へ赴き、警察に摘発されると事件の揉み消しを図った。
あれ? この新聞の記事が1948年6月、で、この事件は1948年11月・・・?
どうやら、判決の出た日をそのまま書いていたようである。
また、衣類についても購入は自由ではなく、「衣料切符」によって制限されていたようである(衣料切符(イリョウキップ)とは – コトバンクより)。
この衣料切符の点数が、水着などで緩和されるというニュース。
日本にも、このような貧しい時代があったということが、この新聞一つとっても垣間見える。


-150x96.png)