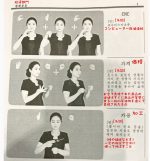さあ今日は中リアス線の開業鉄と洒落込みますよ。
のんさん、三陸鉄道リアス線の開通式典に あまちゃん演じ「思い入れある」https://t.co/mBbPoYFQ6U pic.twitter.com/7g8ESjxCFJ
— 北海道新聞 (@doshinweb) 2019年3月23日
まずは9:02の久慈行きに乗りたい。
そう思って釜石駅の隣のホテルでたらふく食い、ロビーのポスターを見てみると、「釜石の鉄道展」なんてのをやっているという。
釜石といえば、明治の初年に釜石鉱山の鉄道が走っていたお土地柄。
これはもしかしたら良い物が見れるかもしれない。
しかし開催する釜石市民ホールの開場は9時。
仕方がないので、これは1本見送ってこちらを見学することにしたい。
 釜石駅のすぐ裏の大渡橋を渡る。
釜石駅のすぐ裏の大渡橋を渡る。
左手は釜石の中心街、背後は釜石製鉄所である。
かつては、新日鉄釜石のラグビー部が7連覇を達成したこともある。
しかし現在は鎔鉱炉も無くなっている。
(決死モデル:チームY城ヶ崎)
ちなみに製鉄所の全盛期、ここから製鉄所が見えることはなかった。
なぜなら橋上市場があったからである。
これはこれで有名な場所であった。
夕張ほどではないにせよ、すっかり寂れてしまった釜石の街並みを歩いて市民会館を目指す。
そして釜石市民ホールへ。
明らかに震災後復興事業として建設されたと思しき建物である。
 基本的には、三陸鉄道中リアス線の全線開通を記念して開催されたもので、三陸鉄道に関する展示がメインとなる。
基本的には、三陸鉄道中リアス線の全線開通を記念して開催されたもので、三陸鉄道に関する展示がメインとなる。
また、現在は釜石線にC58のSL銀河号が走っており、盛岡市の運動公園に静態保存していたものをどのように復旧したかなどについて書かれてあった。
ちなみに客車はJR北海道の札沼線を走っていた51系客車改造のキハ140を郡山工場で改造している。
裏に回ると、社線(釜石鉱山鉄道)に関する展示があった。
タブレットの玉や、洞泉行きのサボなんてのもある。
釜石は、夕張というよりは室蘭に似ている・・・ってそれは当然で、室蘭も製鉄所の町である。
見ること自体は大して時間がかかるわけでもなく、あとは釜石駅に引き返すだけ。
 とは言っても10:58の宮古行きまで結構時間がある
とは言っても10:58の宮古行きまで結構時間がある
三陸鉄道の釜石駅の前には、ラグビーの町であることを示すモニュメントがある。
(決死モデル:チームPペギー)
現在は新日鉄釜石のラグビー部は「釜石シーウェイブス」というクラブチームになっている。
また、今年開催されるラグビーのワールドカップではこの釜石市も会場になっている。
ただ、ここにホテルを取るとなるとなかなか厳しそうである。
とりあえず、発車までの時間を刷くためにブログでも付けることにしようか。
しかし三陸鉄道の駅の待合室は寒い。
それに比べてJR駅の待合室は暖かさが段違いである。
やっぱり国鉄だね・・・
さて、そんなこんな書いてたら良い時間になったので、ホームへと向かいましょう。
 釜石線の1〜2番線にはすでに花巻行きが待機している。
釜石線の1〜2番線にはすでに花巻行きが待機している。
しばらくすると、盛岡から来た快速「はまゆり」が3番線に到着した。
そして我らが三陸鉄道中リアス線も到着・・・
ありゃ? 横浜博から流れてきたレトロ車?
なんだか得した気分になってしまった。
ともかくも出発。
鉄の町・釜石を左手に2両編成は出発。
かつての山田線のルートを走るが、左手(山側)には三陸自動車道が一部開業しており、深山の趣はない。
ところで、鵜住居を発車しようとした時・・・
向かいの席に座っている小学生が、こちらに向かってビデオカメラを向けているではないか。
ちょっと待て。明らかに俺を撮ってるだろ。どういうつもりだ?
その小学生は太い眉毛がつながっており、知能はあまり高くなさそうである。
何か問題が発生した時に役立つかどうかは分からないが、とりあえずこちらも眉毛繋がり小学生君を撮ることにした。
向こうは大して撮られることを気にしていないようだった。
 さて、大槌に到着。
さて、大槌に到着。
大槌駅は、東日本大震災で完全に流失した駅であり、かなり被害が甚大であった。
現在は島式ホーム1面2線の駅として復活を遂げている。
(決死モデル:チームPウメコ)
駅の中も周辺も、復興系の店が立っている。
さて、ちょっと町歩きしてみますか・・・
とは言っても、駅前の中心街であるにもかかわらず、家並みはまばらで、遠くまで見渡すことができる。
震災から8年、復興も道半ばというところであろう。
とはいえ、新たに図書館ができるなど箱モノは順調にできている印象がある。
 そして大槌町役場跡へ。
そして大槌町役場跡へ。
東日本大震災ではここで町長以下30名もの役場職員が死亡した。
それで助役が町長職務を代行し、助役まで任期が切れた後は総務課長が町長職務を代行した。まるで「シン・ゴジラ」で平泉成演じる農林水産大臣が臨時首相を務めたように。
そして南三陸町同様、ここも被災した庁舎を残すかどうかで議論になったようである。
おおむね、老齢世代は「つらい記憶を思い出すから取り壊してほしい」、若い世代は「震災を語り継ぐために残してほしい」という論調だった記憶がある。
そして、こうして取り壊されたのを見ると、老齢世代の意見が勝ったようである。
 さて、この先取り立て見るものもないので、大槌駅に戻りましょう。
さて、この先取り立て見るものもないので、大槌駅に戻りましょう。
(決死モデル:チームPみく)
「南部鼻曲がり鮭」で有名な大槌町はまた、人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルとなる島があることでも有名であり、拙ブログでも行ったことがある。
それで、大槌駅の駅舎のデザインは、町民の投票でひょうたん島の形になったということである。
2階のテラスには上がることができて、大槌の街並みや海を一望することができる。
そして大槌駅の中には食堂があり、磯ラーメンを食べることもできる。
町おこしの中心として機能していくことになるだろう。
 そして、駅内の至る所に「ひょっこりひょうたん島」のキャラクターの像がある。
そして、駅内の至る所に「ひょっこりひょうたん島」のキャラクターの像がある。
駅のホームを見渡せる所には、ドン・ガバチョの像が立っている。
自分がリアルで見ていた頃は、声は名古屋章がやっていた。
ドン・ガバチョの自己顕示欲はまさに政治家をカリカチュアライズしており分かりやすくて好きだった。
しかし、登場人物の中で一番好きだったのは、小学校のサンデー先生である。
サンデー先生はとにかく教育熱心な教師の鑑だったと思う。
さて、そろそろ12時32分の宮古行きが来るのでホームへ行きましょう・・・
大槌駅は、宮古方面の列車が来ると、無慈悲に構内踏切が閉まるようである。
それで、発車の数分前にはホームにいないといけないということになる。
 そして大槌駅の隣駅は吉里吉里駅となる。
そして大槌駅の隣駅は吉里吉里駅となる。
かつては井上ひさしの「吉里吉里人」として有名になった場所である。
(決死モデル:チームY楼山)
ただ、その「吉里吉里人」を読んだことがあるが、「吉里吉里国」で上野発青森行きの急行「十和田」がジャックされたのは、東北本線の線路上だった。
作中では吉里吉里国は、山田線ではなく宮城県の東北本線上にあったのだ。
「吉里吉里人」以外にも、「青葉繁れる」や「野球盲導犬チビの告白」などで、井上ひさしは好きだったけど、後年動物虐待やDVの話を聞き、いっぺんに自分の中での評価は地に墮ちてしまった。
考えてみれば、「青葉繁れる」は作者自身の仙台一高時代の思い出を書いた物であったが、自分たちは楽しかっただろうが、周囲に迷惑かけてそれを「青春」の一言で済ませてしまうというのには異和感を感じたものだった。
その異和感を一言で言いあらわしてくれる「ホモソーシャル」という言葉に出会ったのは割と最近のことである。
 大槌町の北には山田町がある。
大槌町の北には山田町がある。
大槌は上閉伊郡(釜石・遠野)であるが山田は下閉伊郡(宮古)となる。
陸中山田の駅も震災では流されてしまったが、現在は風車の付いた駅として生まれ変わっている。
ここでは列車交換の為め6分停車となる。
しかし、三陸鉄道は集札業務を駅員ではなく運転手が全てやるようになったらしい。
それで一番前の扉しか開かないので、乗降にはやたら時間がかかる。大槌でもそうだった。(おかげで犠影時間が確保できたのだが)
そして宮古市内に入ると、払川と八木沢宮古短大の2駅が新しく開業した。
三陸鉄道になってからというもの、そういった融通がききやすくなったのだろう。
 そして終点・宮古に到着。
そして終点・宮古に到着。
3番線にはなぜか「リゾートしらかみ」が停まっている。
秋田方面から何か臨時列車でもあるのだろうか。
(決死モデル:チームY宇崎)
ともかくも駅に出てみる。
最近の宮古駅はJRも三鉄も共用駅舎らしい。
そして三陸鉄道の駅舎だった建物は本社機能だけが残っている。
ところで、盛岡行の改札時刻になるとやたら混んでいる。
普段からこれだけ乗っていれば106急行バスに食われJR北海道並みの閉散線区にはなるまいに・・・
と思ったら、どうやらさっきのリゾートしらかみが臨時快速として走るらしい。
 ところで、宮古といえば岩手県北バスの天下である。
ところで、宮古といえば岩手県北バスの天下である。
盛岡との行き来は山田線以上に県北バスの106急行というほどである。
それも、八幡平や陸中海岸国立公園といった観光路線を多く擁しているのと、組合が弱いのとで田舎のバス会社にしてはかなり経営が良い方なのだという。
割と最近まで、県北バスといえば前扉ばっかりというイメージを持っていたが、最近では宮古市内でも2扉車が平気で走る。
そうこうしている間にも、山田線の仇敵であるところの106急行が客を乗せて盛岡へ出発していった。
 さて、久慈行きであるがこちらは駅から一番近い1番線からの発車となる。
さて、久慈行きであるがこちらは駅から一番近い1番線からの発車となる。
JRと共用となった宮古駅では、改札業務は三陸鉄道の社員がやっているらしい。
JRの改札まで引き受けることで、いくらかでも三陸鉄道の収入になっているのだろうか。
かれこれ30年選手となってしまった36系のつり革は、ラグビーボールや鮭の形をして木工の細工になっている。
こうして林業もアピールしているようである。
さて、本降りの雨の中を15時10分に久慈行きは出発。
「三陸鉄道」とはいうものの、リアス式海岸だけに全て浜辺を走るというのは無理で、割とトンネルだらけである。
一ノ渡あたりでは、さっきまでの雨が完全に雪になっていた。この辺りは山側の地形である。
 そして田老で列車交換のため3分停車。
そして田老で列車交換のため3分停車。
(決死モデル:チームWBノノナナ)
高い防波堤を誇っていた田老町であったが、東日本大震災ではまるで役に立たず、市街地が壊滅してしまった。
それで、この通り田老駅周辺には何もない。停車したところで客がいるのかどうか・・・
その代わりに、この田老駅の北側に市街地ができており、こちらに「新田老駅」ができるらしい。
確かに「駅の位置間違ってません?」と思うような場所は全国に多々ある。たとえば網走の桂台駅など。
ところで、三陸鉄道というのは本当にトンネルだらけで、景色が見えないのはまだしも、WiMAXはおろかドコモの携帯すら入らないという区間が多すぎてかなわんわ・・・
島越駅は、三陸鉄道の中でも東日本大震災の被害を甚大に受けた駅として知られている。
それまでは海側に面して南欧風の駅舎があったが、完全に流されてしまった。それも、高架橋の上の駅だったので、線路もろともなくなってしまったのである。
改築してからは、山側に駅舎を改築し、元々の駅舎の跡地には慰霊碑のような碑と、かつての南欧風の駅舎の塔屋が残っているだけとなってしまった。
ただ、そんな慰霊碑を建てるほどの犠牲者が島越で出たのかと思ったら、wikipediaで調べたところでは慰霊碑だと思ったのは宮沢賢治の詩碑だったらしい。
2両編成の列車はなおも北へ向かう。
 「海岸」とは名ばかりの山奥にある白井海岸駅を出て、長いトンネルを抜けると、太平洋の波が荒々しくぶつかりあう。
「海岸」とは名ばかりの山奥にある白井海岸駅を出て、長いトンネルを抜けると、太平洋の波が荒々しくぶつかりあう。
そう思ったら列車は停止した。
(決死モデル:チームR園田)
ここはNHKの「あまちゃん」でも有名となった絶景の大沢橋というのだそうな。
運転手のアナウンスでは「あいにくの天気となりましたが・・・」とのことだが、なかなかどうしてこのような日本海のような荒波も悪くない。
ところで、左向きメンでよくやる流し目アングルを、右向きメンである園田で初めてやってみたが、こんな髪型になるとは知らなかった。
 観光停車は何も大沢橋だけではない。
観光停車は何も大沢橋だけではない。
安家川橋梁も観光停車スポットとなっているようである。
PCトラス橋梁としては最大の規模になるのだそうで、ここからも三陸海岸の絶景を拝むことができる。
また、山側を見ると、三陸自動車道が建設されており、安家川の上流には鮭の孵化場が建設されているという。
あとは、列車は終点の久慈を目指すだけ・・・
(文字数ランキング37位、3.6パーセンタイル)