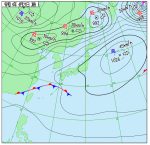最近のAIは文豪もやってくれるらしい。
「第2サリドマイド事件」「ヴィーナス児」に関する一連の報道を作成してもらった。
目次
全国で相次ぐ「両腕欠損の女児」出生 原因不明の異常、専門家も困惑
令和XX年5月22日 恐慌新聞 朝刊社会面
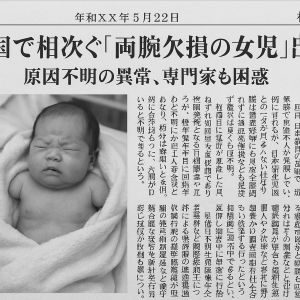 近月、日本各地の病院で両腕が肩から欠損した状態で生まれる女児の報告が相次いでいる。いずれの症例も男児には見られず、女児のみに限定されている点が大きな特徴だ。現在のところ、遺伝子異常・感染症・薬剤等の明確な因果関係は見つかっておらず、原因は不明のままである。
近月、日本各地の病院で両腕が肩から欠損した状態で生まれる女児の報告が相次いでいる。いずれの症例も男児には見られず、女児のみに限定されている点が大きな特徴だ。現在のところ、遺伝子異常・感染症・薬剤等の明確な因果関係は見つかっておらず、原因は不明のままである。
初めに報告があったのは、東京都内の大学病院。令和9年2月、健康に見える女児が両腕のない状態で出生し、医師が都の衛生当局に報告。数日後には、埼玉、長野、兵庫、福岡など複数の地域の産科施設でも同様の症例が確認され、厚生労働省が全国調査に乗り出す事態となった。
調査の初期段階では「環境要因に起因する地域限定の現象」との見方もあったが、報告が急速に全国へと拡大。現在までに確認された症例は62件(いずれも女児)にのぼる。うち9件は同月内の同時多発的な発生であり、偶発的とは考えにくいとの見解が専門家から出ている。
加えて、アメリカ西海岸、ドイツ・ハンブルク、韓国・釜山などでも、類似の女児が数名出生したとの報告があり、WHO(世界保健機関)も情報収集を始めている。
国内の産婦人科医で構成される日本新生児医療学会では、「極めて異例の性差を伴う先天異常であり、サリドマイド禍以来の重大な関心事である」とし、全国規模の妊婦調査および症例の一元管理に着手している。
厚労省は現在、該当する児の母親たちに対し、妊娠中の服薬、居住環境、ワクチン接種歴、食生活、勤務先情報などの詳細な聞き取り調査を実施中であり、必要に応じて国際的な疫学チームの協力も視野に入れるという。
現時点では、メディアではこの先天異常の児を、ミロのヴィーナス像になぞらえて「ヴィーナス児」と呼ぶ報道も見られ、呼称の是非も議論され始めている。
厚労省・大学病院が緊急調査 女児に限った先天異常、原因特定できず
令和XX年6月4日 恐慌新聞 朝刊一面
 全国で報告が相次いでいる「両腕欠損の女児」出生例について、厚生労働省は3日、国立成育医療研究センターや複数の大学病院と連携し、緊急調査チームを発足させたと発表した。調査は、ゲノム(全遺伝情報)解析や、妊婦の生活環境に関する詳細なデータ収集を含む本格的なものとなる。
全国で報告が相次いでいる「両腕欠損の女児」出生例について、厚生労働省は3日、国立成育医療研究センターや複数の大学病院と連携し、緊急調査チームを発足させたと発表した。調査は、ゲノム(全遺伝情報)解析や、妊婦の生活環境に関する詳細なデータ収集を含む本格的なものとなる。
調査チームでは、AI(人工知能)を用いた母体の生活履歴解析や、全国の出生記録との照合、食品・医薬品・水質・大気中化学物質の相関調査も並行して進められている。しかし、現時点では異常の共通因子は見つかっておらず、原因の特定には至っていないという。
今回の先天異常が、女児にのみ限定して発生しているという事実が、医学界にとっても大きな謎となっている。国立遺伝学研究所の専門家は「これほど極端な性差を伴う先天異常は極めて稀。性染色体による選択的な影響や、未知の性差因子が関与している可能性がある」とコメントした。
また、WHO(世界保健機関)もこの事象に注目しており、日本を中心とした国際共同研究体制の構築も視野に入れられている。
「ヴィーナス児」呼称が拡散 SNSで共感と波紋 「令和のサリドマイド」社会に広がる不安
令和XX年6月17日 恐慌新聞 夕刊 社会面
 全国で報告が続く両腕欠損の女児の出生異常について、SNSやテレビ報道を通じて社会的関心が急速に高まっている。Twitter(現X)やInstagramでは、当事者家族や医療関係者による投稿が相次ぎ、ネット上ではこの現象を「令和のサリドマイド事件」と表現する声が拡大。国民の間に不安と動揺が広がっている。
全国で報告が続く両腕欠損の女児の出生異常について、SNSやテレビ報道を通じて社会的関心が急速に高まっている。Twitter(現X)やInstagramでは、当事者家族や医療関係者による投稿が相次ぎ、ネット上ではこの現象を「令和のサリドマイド事件」と表現する声が拡大。国民の間に不安と動揺が広がっている。
こうした状況の中、今月15日に放送された某民放局のドキュメンタリー番組が大きな波紋を呼んだ。番組では、両腕が存在しない新生児の姿を映像とともに紹介し、ナレーションの中で「まるでミロのヴィーナス像のようだ」と表現。視聴者の間で「美と障害の象徴が重なる」といった肯定的な反応と、過度な美化ではないかという批判が交錯した。
しかし、放送後にはSNS上でこの子どもたちを「ヴィーナス児」と呼ぶ表現が拡散。翌日にはTwitterの日本トレンド上位に入り、TikTokやYouTubeでも「ヴィーナス児」に言及する動画が次々と投稿された。
厚生労働省は現時点で正式な呼称を定めていないが、医学会の一部ではすでに「ヴィーナス症候群」という仮名称が使われ始めているという。
一方、妊娠中の女性たちの間では強い不安が広がっており、出生前診断の希望者が急増。一部の自治体では相談窓口が混雑するなど、現場が混乱している。産婦人科医会は「冷静な対応と情報提供が求められる」と呼びかけているが、出産を控える動きや妊娠自体を見送る夫婦も増えているという。
政府、「ヴィーナス児」問題に本腰 内閣に対策本部設置 福祉・教育・技術開発を一体支援へ
令和XX年7月2日 恐慌新聞 朝刊 政治・社会面
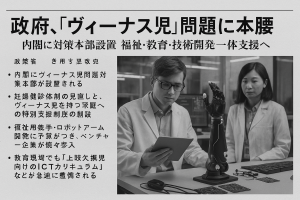 全国で相次ぐ両腕のない女児の出生異常(通称:ヴィーナス児)をめぐり、政府は1日、内閣官房に「ヴィーナス児問題対策本部」を設置した。各省庁の連携による包括的な対策が本格化する。
全国で相次ぐ両腕のない女児の出生異常(通称:ヴィーナス児)をめぐり、政府は1日、内閣官房に「ヴィーナス児問題対策本部」を設置した。各省庁の連携による包括的な対策が本格化する。
厚生労働省は、妊娠初期からのリスク把握を目的として、妊婦健診体制の抜本的見直しを表明。あわせて、ヴィーナス児を育てる家庭に対し、特別支援金や在宅療育サービス、福祉機器助成などを盛り込んだ新たな支援制度が令和XX年度中に導入される見込み。
さらに経済産業省は、福祉用義手やロボットアームの開発に対する助成金制度を創設。東京都内をはじめとする複数のベンチャー企業が、AI搭載の高機能義手や、脳波制御によるインターフェースの開発に着手している。関係者は「医療工学と福祉技術の転換点」と期待を寄せる。
また文部科学省は、**「上肢欠損児向けICT教育カリキュラム」**の整備を全国の小中学校で進めており、タブレット操作、音声入力、視線追跡型デバイスの導入が急ピッチで進む。教育現場では、「支援から共生への転換」がキーワードになりつつある。
対策本部の初会合では、首相が「これは単なる医療課題にとどまらず、日本社会の包摂力が問われている問題だ」と発言。今後は地方自治体とも連携し、地域ごとの支援体制強化が検討される。
「ヴィーナス児」呼称、社会に広がる 美化か共感か、揺れる受け止め方
令和XX年7月9日 恐慌新聞 文化・社会面
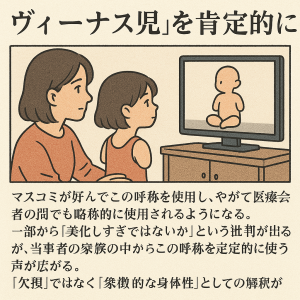 両腕のない女児として生まれた「ヴィーナス児」と呼ばれる子どもたちに対して、その呼称の是非をめぐる議論が社会で広がっている。
両腕のない女児として生まれた「ヴィーナス児」と呼ばれる子どもたちに対して、その呼称の是非をめぐる議論が社会で広がっている。
この呼称は、あるドキュメンタリー番組で赤ん坊を**「まるでミロのヴィーナス像のようだ」と表現**したのをきっかけに拡散。SNSを中心に急速に定着し、現在ではマスコミ各社も見出し等で好んで使用するようになった。
当初は俗称とされていたが、近年では**医療関係者の間でも略称的に「ヴィーナス児」と呼ばれることが増えつつある。**一部の医学論文でも「Venus Syndrome(ヴィーナス症候群)」という形で仮称として用いられる事例が出ている。
一方で、「身体障害を神秘的・美的な象徴に仕立て上げすぎているのではないか」といった、**「美化しすぎ」とする批判の声も上がっている。**特に障害者当事者団体の一部からは「外見的印象に頼る命名には慎重であるべき」との声明も出された。
しかし、**当事者の家族の中にはこの呼称を「前向きに受け止めている」という声も少なくない。**ある母親は「“障害児”と呼ばれるよりずっと誇りを感じる」と語る。保育園や学校現場でも、「ヴィーナスちゃん」と親しみを込めて呼ばれる場面があるという。
この呼称は今、単なる言葉を超えて新たな身体観の象徴として解釈されつつある。近年では国内外のフェミニズムや身体障害学、ジェンダー研究などの分野で「象徴的身体性」や「代替美」の概念として注目され、国際学会でも報告が相次いでいる。
学術界のある研究者は「ヴィーナス児という言葉をどう扱うかは、日本社会が“障害”や“女性性”をどう見ているかの鏡でもある」と指摘している。
“ヴィーナスのまま”舞台へ——義手を拒み、表現者へ進化する新世代
「新しい身体の時代」の胎動か
令和XX年8月12日発行 恐慌新聞 第三社会面
かつて「原因不明の先天性両腕欠損」として国内外を震撼させた「ヴィーナス児」たちが、今やSNSやメディアを通じて自己表現を始めている。出生時に“悲劇の象徴”とされた彼女たちは、今、あえて義手をつけない姿で表舞台に立つことで、旧来の身体観そのものに挑戦している。
X(旧Twitter)やTikTokでは、自らの出生背景や日常生活を語るヴィーナス児による発信が急増中。「#ヴィーナスのまま」「#腕がなくても世界を変える」がトレンド入りするなど、彼女たちの存在は、社会の「正常」の定義を揺さぶり始めている。
中でも注目されているのは、両腕のない状態で義手を使わずにファッションモデルやアーティストとして活動する若いヴィーナスたちだ。ある人気YouTuberは、「この姿でカメラの前に立つことで、みんなの視線に意味を問いたい」と語る。国内外のアート界でも彼女たちの存在は強い注目を集めている。
また、**ヴィーナス児を主人公にした劇場アニメ『ヴィーナス・イレブン』やドラマ化作品『ヴィーナス・レーン』も制作され、すでに若年層を中心に大きな話題を呼んでいる。専門家の間では、「かつて“欠損”とされた身体が、今や“象徴的身体”として文化的価値を帯び始めている”とする声もある。
“異形”が“個性”となり、“障害”が“視点”となる世界へ——
今、「新しい身体の時代」が、確かに始まっているのかもしれない。


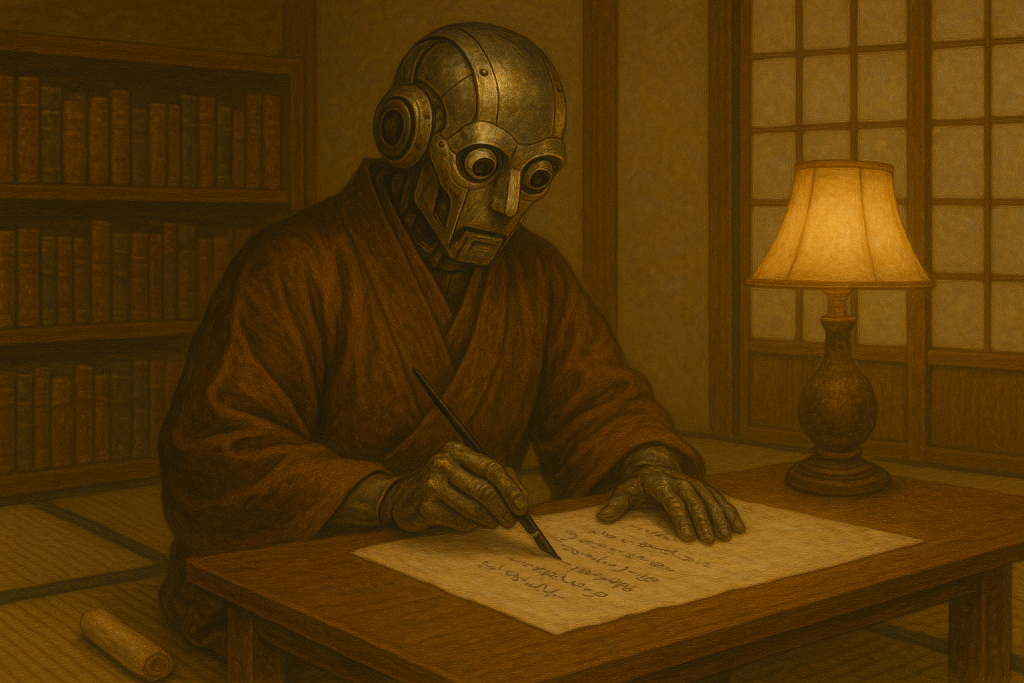






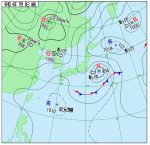
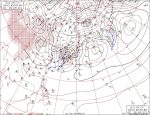


-150x96.png)