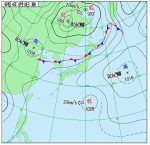社畜なのでちょっとChatGPTに小説書かせてみた。
追い詰められた島
「転勤が決まった」
その知らせを聞いたとき、ゼロは言葉を失った。
50歳を目前にした中堅社員。長年、本社でそれなりにやってきたつもりだったが、ある日突然、東京都の離島・小笠原村父島への異動を命じられた。表向きは「現場経験を積むため」だが、実際は「使えない」烙印を押された結果の左遷だった。
本社勤務の長い大卒の自分が、島の事務所で何をすればいいのか。そんな不安を抱えながら、24時間かけて父島へ渡った。
しかし、その不安はすぐに現実のものとなる。
罵声
24−1――年齢はゼロより年上の高卒のベテラン部下。普通は2年で交代する島の事務所で5年働いている男だった。
「はぁ? こんなこともできねぇのかよ?」
「50にもなって本社育ちってのはこんなにポンコツなのか?」
「てめぇ、仕事の邪魔だからそこに突っ立ってるだけにしろや」
24−1の罵倒は執拗だった。語彙は異様に豊富で、ゼロの自尊心を的確に抉ってくる。
「お前、本社じゃどんな仕事してたんだよ? エラそうにパソコン叩いてただけか?」
「島の空気でも吸ってちっとはマシになれよ、無能」
毎日毎日、罵声を浴びせられる。ゼロは反論できなかった。島の職員は皆24−1に従っていた。彼は事実上、この事務所のボスだったのだ。
「本社の奴らって、ホントに口だけだよなぁ? あー情けねえ」
耐えがたい日々だった。胃が痛む。眠れない。毎朝、事務所へ行くのが怖くなる。
「このままじゃ、俺は壊れる……」
そう思ったとき、ゼロの中で何かが弾けた。
計画
ある日、24−1のスケジュールを確認した。週末、彼は事務所に一人で残る予定だった。他の職員は島の集まりに参加するため、翌朝まで戻らない。
「これしかない……」
ゼロは密かに準備を進めた。
監視カメラの死角を確認し、事務所の物置にバールを忍ばせる。島の地形を調べ、最も発見されにくい無人の崖を探した。
そして、決行の日が訪れる。
実行
週末の夜。事務所にはゼロと24−1だけが残っていた。
「お前、まだ残ってんのか? ほんっとトロいなぁ! 早く帰れよ、邪魔だ」
その言葉が、最後の引き金を引いた。
ゼロは物置に隠していたバールを手に取り、静かに24−1の背後に回った。
「なんだよ、お前――」
振り向いた24−1のこめかみに、全力でバールを振り下ろす。
鈍い音が響き、24−1の体が机に倒れ込む。頭から血が流れ、動かない。だが、まだ息があった。
「お前……この……クズが……」
最後の力で呟いた瞬間、もう一撃、バールを振るった。今度こそ、動かない。
ゼロは震えながら深呼吸し、24−1の体をブルーシートに包んだ。事務所の裏口へ運び出し、車に積み込む。
向かう先は、島の外れにある無人地帯の崖。
崖の向こうへ
夜の海が広がる。波の音が響く。
ゼロは24−1の遺体を車から引きずり出し、崖の縁まで運んだ。
「もう、お前の声を聞くことはない……」
そう呟き、力いっぱい突き落とす。
闇に飲まれる遺体。ゴツゴツした岩にぶつかる音がした後、沈黙が訪れた。
終わった。
ゼロは深く息を吸い、静かにその場を離れた。
捜査と疑惑
翌日、24−1の行方不明が発覚した。
島の警察が動き出したが、所詮は小さな駐在所の警官たち。島は広く、捜索は難航した。
「最近、何か変わったことは?」
警察が事務所の職員に聞く。ゼロにも質問が来た。
「いえ、特に……いつも通りでした」
冷静に答えた。
しばらくして、捜索は打ち切られた。警察は「海に落ちた事故」として処理し始めた。酒に酔って滑落したのだろう、と。
事件ではなく、事故。
ゼロはほっとした。
24−1の声が聞こえなくなって、事務所は静かになった。仕事が楽になった。もう誰にも怒鳴られることはない。
――なのに、なぜか眠れない。
波の音が、夜になると頭の中で響く。
「おい、まだ残ってんのか?」
24−1の声が、暗闇の中で囁くように聞こえる。
ゼロは布団をかぶり、震えた。
終幕
ま、そういう小説ですということで。